「日本酒は太る」「お酒は体に悪い」――
そんなイメージを持っていませんか?
実は、日本酒は“悪者”どころか、**うまく付き合えば「体を整えるやさしい飲み物」**なんです。
その秘密のひとつが、日本酒に含まれる“ミネラル”の存在。
この記事では、
- 日本酒に含まれるミネラルの種類
- どんな健康効果があるのか?
- ミネラル補給に向いた銘柄や飲み方
を、初心者にもわかりやすくご紹介します。
ミネラルって何?なぜ必要?
ミネラルとは、体の調子を整えるために欠かせない栄養素。
ビタミンと並び、「微量栄養素」とも呼ばれます。
現代人に不足しがちな代表的なミネラルは以下の通り:
| ミネラル名 | 主な働き |
|---|---|
| カルシウム | 骨や歯の形成、イライラ予防 |
| マグネシウム | 神経伝達・筋肉の収縮・血圧の調整 |
| カリウム | 体内の水分バランス調整、むくみ予防 |
| リン | エネルギー代謝、細胞膜の構成成分 |
| 亜鉛 | 免疫力アップ・味覚や皮膚の健康を保つ |
サプリや栄養ドリンクで補う人も多いですが、実は日本酒にもこれらのミネラルが自然に含まれているんです。
日本酒に含まれるミネラルの理由
日本酒の原料は、「水・米・麹」だけというシンプルな素材。
この中でも、ミネラルの供給源となるのが以下の2点です。
① 醸造水(仕込み水)
日本酒の80%以上を占めるのが「水」。
使用される水には、その土地ならではのミネラル成分が含まれており、これが酒質や体への影響に大きく関わっています。
たとえば:
- 硬水系 → カルシウム・マグネシウムが豊富(兵庫・福井など)
- 軟水系 → カリウムやナトリウムが穏やかに含まれる(新潟・秋田など)
② 米と米麹
精米度によってミネラルの量は変わりますが、特に純米酒や精米歩合の低い酒には、ミネラルが多く残る傾向があります。
麹の分解作用により、ミネラルが体に吸収されやすい形に変化するのもポイントです。
ミネラル補給としての日本酒の健康効果
✅ 疲労回復をサポート
カリウムやマグネシウムは、筋肉の緊張をゆるめ、神経伝達を正常に保つ働きがあります。
仕事終わりや運動後の晩酌として、少量の日本酒を取り入れると、体と心がホッとするリセットタイムになります。
✅ むくみ予防&血圧調整
カリウムはナトリウムの排出を促すため、むくみやすい人にとっての救世主。
また、適量のアルコールと一緒に摂ることで、血管が広がり血流も改善されるため、冷え性や高血圧予防にも◎。
✅ 睡眠の質が向上
マグネシウムには、メラトニンという“睡眠ホルモン”の生成を助ける働きがあります。
寝る前に少量の日本酒を飲むことで、リラックスしやすくなり、深い眠りへつながるという研究結果も。
ミネラルを意識する人におすすめの日本酒タイプ
| タイプ | 特徴 | 銘柄例 |
|---|---|---|
| 純米酒 | 米と麹だけで造られ、ミネラルやアミノ酸が豊富 | 「五橋 純米」(山口)「真澄 純米」(長野) |
| 生酛・山廃仕込み | 発酵がしっかりしており、ミネラル成分が濃厚 | 「大七 生酛純米」(福島)「天狗舞 山廃純米」(石川) |
| にごり酒 | 米粒や麹が多く残り、ミネラル・ビタミンがそのまま摂れる | 「白川郷 にごり酒」(岐阜)「月の井 にごり酒」(茨城) |
効果的に“飲むミネラル”を摂るポイント
- 1日1合(180ml)までが理想的
- 食事と一緒に摂ることで吸収効率がUP
- 常温〜ぬる燗で飲むと胃腸にもやさしく、代謝もサポート
さらに、野菜や海藻など“ミネラルを含むおつまみ”と合わせることで、相乗効果が期待できます。
おすすめ!ミネラル豊富なおつまみ3選
| おつまみ | 特徴 |
|---|---|
| ひじきと大豆の煮物 | カルシウム・鉄・マグネシウムが豊富で整腸にも◎ |
| 枝豆+塩少々 | カリウムたっぷり&低カロリー。ビールじゃなく日本酒とも合う |
| きゅうりの酢の物+わかめ | ミネラル+酢の効果で疲労回復を助けてくれる |
まとめ|日本酒は「おいしく飲めるミネラル習慣」
- 日本酒には、米と水に由来するミネラルが豊富に含まれている
- 疲労回復、血流改善、むくみ対策、睡眠サポートなどにうれしい効果が期待できる
- 飲み方・選び方・食べ合わせを工夫すれば、健康的な晩酌習慣が実現!
「お酒は健康の敵」と思っていたあなた。
これからは、“飲んで整えるお酒=日本酒”として、1杯の中に込められた栄養の力を楽しんでみませんか?


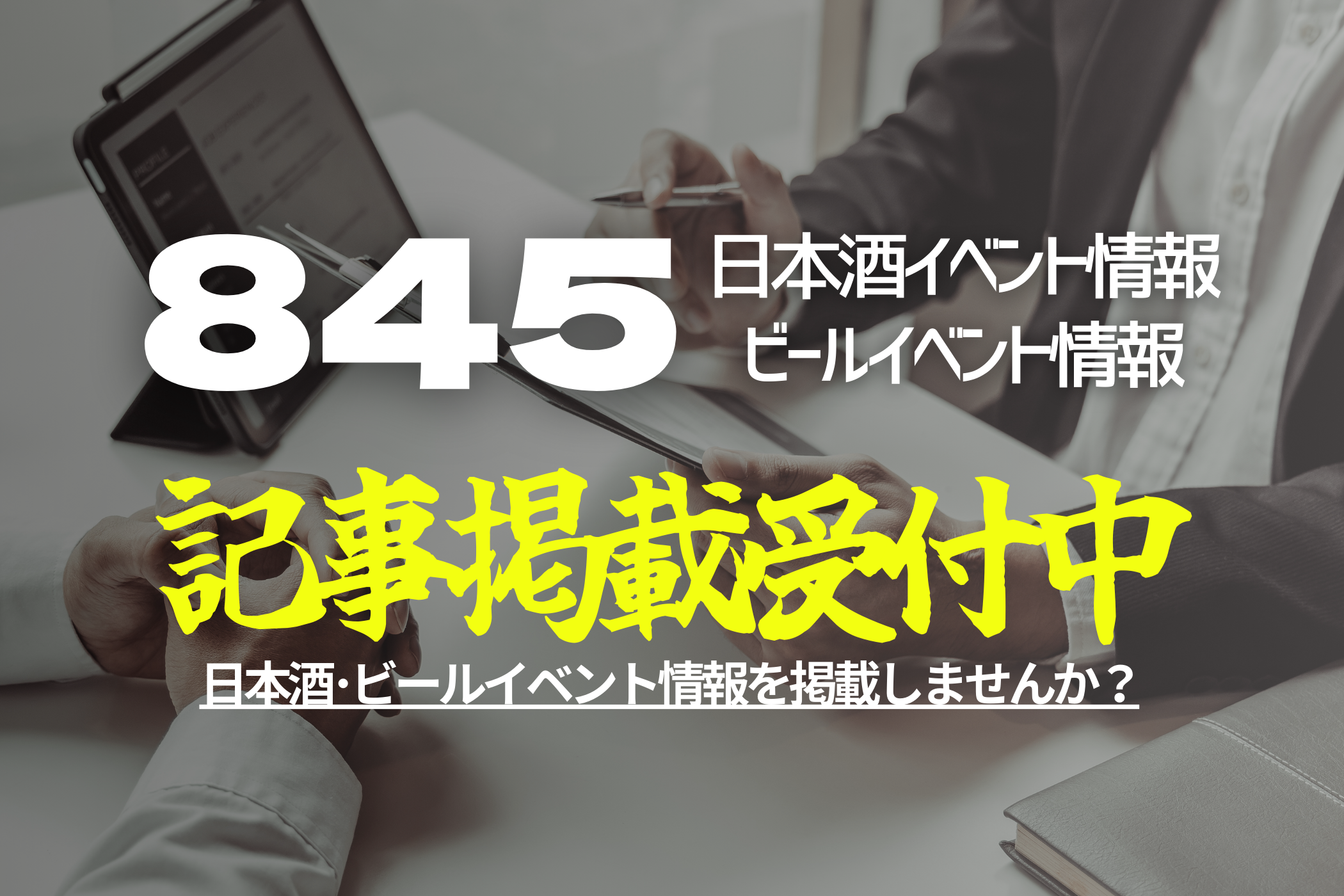
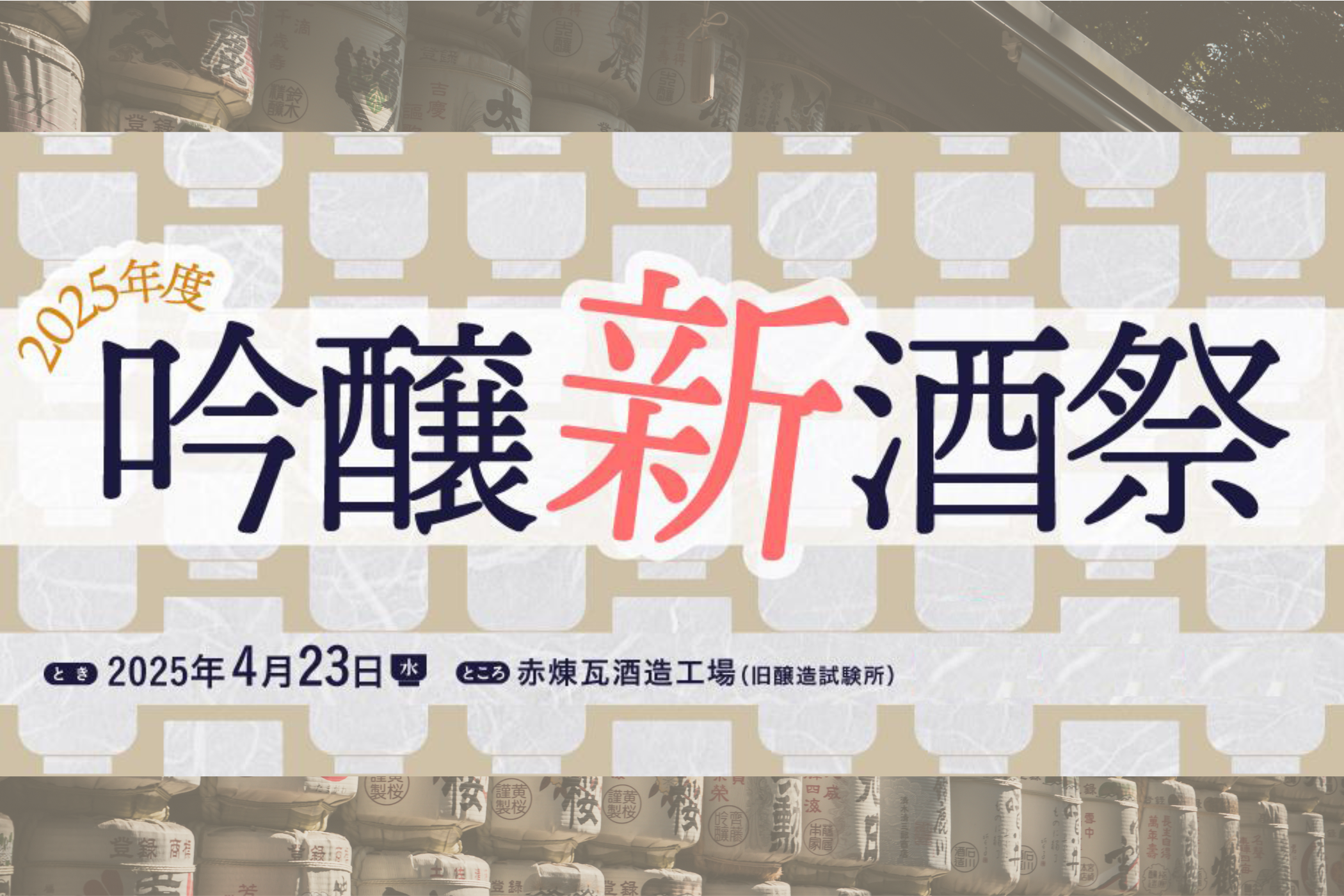




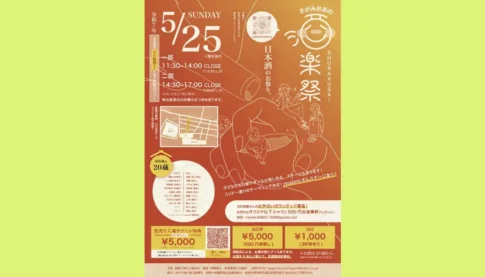



コメントを残す