日本酒の中でも「吟醸づくり」という特別な製法でつくられているのが「吟醸酒」です。
フレッシュで華やかな香りを持つお酒です。
吟醸酒は「冷酒」で飲むことで、味わいを楽しむことができます。
では、吟醸酒とは一体どんなお酒なのでしょうか。
今回は、日本酒の「吟醸酒」とは何か・吟醸づくり製法・特徴・歴史・種類について、どこよりもわかりやすくご紹介します。
「吟醸酒」とは何か?
吟醸酒とは精米歩合が60%以下で、吟醸づくり製法でつくられた、香味、色沢が良好なお酒のことです。
吟醸酒の読み方は「ぎんじょうしゅ」と読みます。
1⃣精米歩合が60%以下とは?
精米歩合が60%以下とは、玄米を精米した時に、削って残った部分が60%以下であるということです。
2⃣吟醸酒が精米歩合を60%以下にする理由
吟醸酒が精米歩合を60%以下にする理由は、玄米の表層にあるタンパク質や脂肪分を削ることで雑味を取り除き、スッキリしたキレイな味わいにするためです。
3⃣吟醸づくり製法とは何か?
吟醸づくり製法とは国税庁の定義では次の通りです。
「吟醸造りとは、吟味して醸造することをいい、伝統的に、よりよく精米した白米を低温でゆっくり発酵させ、かすの割合を高くして、特有な芳香(吟香)を有するように醸造すること」(原文ママ)
次の章では「吟醸づくり製法」について、さらにわかりやすくご紹介します。
「吟醸づくり製法」の流れをわかりやすく解説
こちらでは吟醸づくり製法がどんなものなのかについてわかりやすく解説します。
1⃣精米歩合60%以下まで精米した白米を原料にする
2⃣突破精の麹米をつくる
突破精(つきはぜ)の麹米とは、お米の内部に深く根を張る麹のことで、吟醸酒などのようにスッキリした淡麗系のお酒に向いた麹米のことです。
突破精とは麹のことです。
現在日本酒の麹には「突破精型」と「総破精(そうはぜ)型」の2種類があります。
それぞれ日本酒の種類によって使い分けられています。
3⃣10度前後の低温で1カ月近い時間をかけて「もろみ」を発酵させる
低温長時間発酵をする理由は香味成分を多く生成させ、もろみに閉じ込めるためです。
4⃣上槽(じょうそう)ではゆるく搾り、酒粕歩合を高める
5⃣結果「吟醸香(ぎんじょうか)」が立ち昇るフルーティーな香りの吟醸酒ができあがる
吟醸香とは、吟醸酒や大吟醸酒から立ち昇る甘い果実や花のような華やかな香りのことです。
「吟醸酒」の歴史
日本酒の歴史に「吟醸」という言葉が登場したのは明治維新以降からです。
江戸時代までは酒樽の絵や焼き印のひな型に「吟造」「吟製」と入れられていました。
意味は「謹んでつくる・謹製」という意味です。
日本で始めて「吟醸」という言葉が使われたのは明治27年(1894年)です。
新潟県の酒造家の岸五郎の著作「酒造のともしび」からでした。
さらに各酒蔵は技術を向上させるために「吟醸酒」という名前を冠して各地の鑑評会や品評会へ出品し始めます。
ただし当時は精米歩合が低い吟醸酒でした。
吟醸酒にとって大きな転機になったのが昭和8年(1933年)です。
精米歩合を高めることができる「竪型精米機」が登場したからです。
竪型精米機とは、精米歩合50〜60%の精米が可能な精米機でした。
これにより本格的な吟醸酒や大吟醸酒がつくれる可能性が高まります。
そして1982年に日本で「吟醸酒ブーム」が起こり現在に至ります。
「吟醸酒」の特徴
こちらでは吟醸酒の特徴についてご紹介します。
❶味わい
吟醸酒の味わいはスッキリとした淡麗で、のどごしがなめらかで、飲みやすい味わいです。
お米の旨味や風味を感じることができるお酒です。
❷香り
吟醸酒の香りは「吟醸香」がする香りです。
吟醸香とは吟醸酒独特の香りのことで、フルーティで華やかで、甘い果実や花のような香りです。
具体的にはリンゴのような香り、バナナのような香りが立ち昇っています。
❸後味
吟醸酒の後味は、スッキリ、爽やかで、後を引かない引き締まった後味です。
❹アルコール度数
吟醸香のアルコール度数は15度前後です。
❺吟醸酒の種類
吟醸酒の種類は次の4種類です。
1⃣吟醸酒
吟醸酒とは精米歩合60%以下、吟醸づくり製法でつくられ、醸造アルコールが加えられているお酒です。
2⃣純米吟醸酒
純米吟醸酒とは精米歩合60%以下、吟醸づくり製法でつくられ、醸造アルコールなしのお酒です。
純米吟醸酒は米・米麹・水だけでつくられていることから、お米の旨味やコクがはっきりと感じることができます。
3⃣大吟醸酒
大吟醸酒とは精米歩合50%以下、吟醸づくり製法でつくられ、醸造アルコールが加えられているお酒です。
吟醸酒よりもより雑味が少なく、フルーティーで華やかな香りがします。
4⃣純米大吟醸酒
純米大吟醸酒とは精米歩合50%以下、吟醸づくり製法でつくられ、醸造アルコールなしのお酒です。
純米酒の持つお米の旨味やまろやかさがあり、さらに大吟醸酒の持つ華やかでフルーティな香りが感じられます。
まとめ
今回は、日本酒の「吟醸酒」とは何か・吟醸づくり製法・特徴・歴史・種類についてご紹介しました。
吟醸酒はスッキリしてクリアな飲み応え、フルーティで華やかな香りが持ち味の日本酒です。
初めて吟醸酒を飲む方は、まずは「冷酒」で飲んでみることをおすすめします。





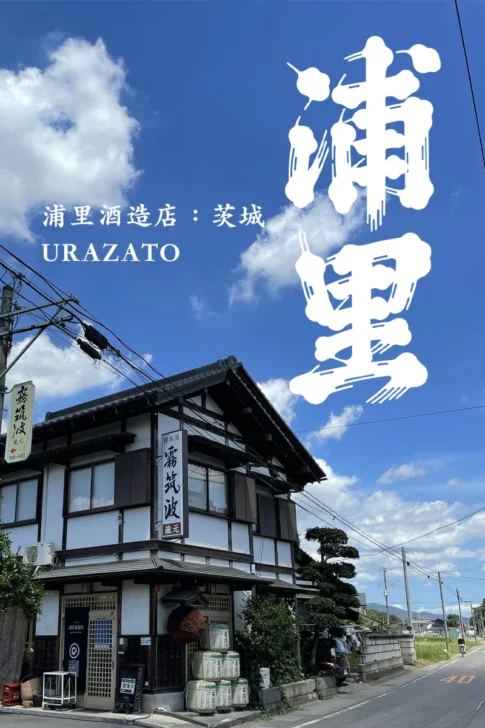






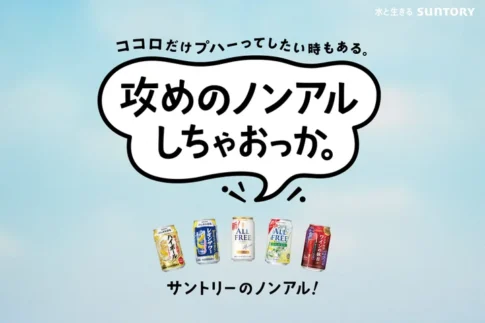
コメントを残す