日本酒の中には「醸造アルコール」が添加されているお酒があります。
本格派の日本酒を飲みたい方からすると若干微妙な気持ちかもしれません。
実際、醸造アルコールが添加されると元の日本酒の味わいや香りは変わります。
では、醸造アルコールとは一体どんなものでしょうか。
今回は、なぜ、日本酒には「醸造アルコール」が使われているのかについて、どこよりもわかりやすくご紹介します。
醸造アルコールとは何か?
醸造アルコールとは主にサトウキビを原料にしたアルコール度数45度超えまで蒸留した食用エタノールのことです。
食用エタノールとは食品にも添加することができるアルコールのことです。
醸造アルコールの原料には廃蜜糖(サトウキビの搾りかす)・トウモロコシ・お米などが使われます。
醸造アルコールを添加したお酒、しないお酒の名称
醸造アルコールを添加したお酒をアルコール添加酒(アル添酒)といいます。
具体的には吟醸酒・大吟醸酒・本醸造酒・普通酒などです。
また醸造アルコールを一切添加してないお酒を純米酒といいます。
一般的に鑑評会に出品されるお酒は、醸造アルコールが添加された大吟醸酒が主に出品されます。
日本酒に醸造アルコールを添加する4つの理由
こちらでは日本酒に醸造アルコールを添加する4つの理由についてご紹介します。
❶お酒の腐敗を防ぐため
1つ目の理由はお酒の腐敗を防ぐためです。
お酒はアルコール度数が高く、微生物が存在できない環境であれば腐敗はしません。
具体的には焼酎やウイスキーなどです。
ところがアルコール度数が低く、糖類があり、火入れがされてないと腐敗することがあります。
具体的には日本酒やブドウ酒などです。
お酒にアルコール度数の高い醸造アルコールを添加することで、お酒の腐敗を防ぐことが可能です。
❷お酒の味わいを軽くするため
2つ目の理由はお酒の味わいを軽くするためです。
醸造アルコールを添加する前のお酒は「もろみ」の状態です。
もろみをそのまま搾ると「原酒」や「純米酒」ができあがり、かなり濃淳でボリューム感があります。
そのため一般の人からすると重くて飲みにくく感じるお酒です。
ところがもろみの時に醸造アルコールを添加すると、搾った後に味わいがスッキリ、軽快で、爽やかになります。
すると全体的に軽くなり、一般の人でも飲みやすいお酒になります。
❸お酒に「吟醸香(ぎんじょうか)」を立てるため
3つ目の理由はお酒に「吟醸香」を立てるためです。
吟醸香とはフルーティで華やかで、甘い果実や花のような香りのことです。
日本酒にはもろみを搾って「原酒」と「酒粕」を分ける工程があります。
ただし日本酒はもろみの状態でフルーティですが、搾ると香りの成分のほとんどは酒粕に移ってしまいます。
この香りの成分を日本酒の原酒に残すために使われるのが醸造アルコールです。
これは香りの成分がアルコールに溶け込むという性質を利用したものです。
醸造アルコールを添加することによって本来酒粕に移るかもしれない香りを醸造アルコールに溶け込ませる狙いで使われています。
❹販売コストを下げるため
4つ目の理由は販売コストを下げるためです。
日本酒を原酒や純米酒のまま出荷すると、旨味があり、濃度が高いお酒ですが、販売コストは高くなります。
そのため原酒や純米酒のままで売ろうとすると高値で売らなければなりません。
そうなるとビールや焼酎との価格競争に負けてしまう恐れがあります。
ところが醸造アルコールを添加すると、味わいは軽くなりますが、美味さは同じで香ちが立ち、しかもリーズナブルな価格で売ることができます。
品質を保ちながら販売コストを下げるために醸造アルコールは使われています。
日本酒に醸造アルコールを添加するタイミング
日本酒に醸造アルコールを添加するタイミングは「上槽(じょうそう)」の1日前に添加します。
上槽とはもろみを「原酒」と「酒粕」に分ける工程のことです。
上槽の1日前にもろみに醸造アルコールを添加する理由は、そのままでは酒粕に奪われるであろう「吟醸香」を醸造アルコールに溶け込ませるためです。
醸造アルコールはどうやってつくられているのか?
醸造アルコールのつくり方は「焼酎」とほぼ同じです。
1⃣日本酒と同じ要領で原料を発酵させ初期アルコールをつくる
2⃣初期アルコールを蒸留する
3⃣アルコール濃度を高め、45度を超えたら「醸造アルコール」の完成
また醸造アルコールに水を入れてアルコール度数36度未満に薄めると「甲類焼酎」になります。
醸造アルコールを飲んでも安全なのか?
醸造アルコールは安全なアルコールです。
醸造アルコールは人工的につくられた合成アルコールなどの化学製品では一切ありません。
そのため人が飲んでも過度な飲酒でなければ健康に害はありません。
理由は醸造アルコールの原料は天然由来の穀物類だからです。
また醸造アルコールは単体でも販売されています。
醸造アルコールの酒税法での位置づけ
現在、醸造アルコールは国産の日本酒全体の76.9%に添加されています。
醸造アルコールを添加した日本酒は厳密には「清酒」ではありません。
混成酒(リキュールではない)になります。
ただし酒税法では「清酒」として扱われます。
まとめ
今回は、なぜ、日本酒には「醸造アルコール」が使われているのかについてご紹介しました。
お酒に詳しくなってくると「醸造アルコール入りのお酒はどうも・・・」という人は一定数います。
ただし実際はお酒が飲みやすくなり、吟醸香が立ち、価格がリーズナブルになるので、醸造アルコール入りはアリではないでしょうか。











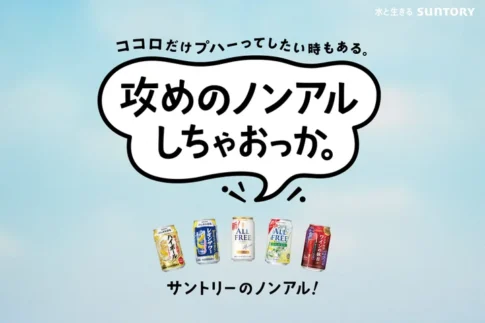
コメントを残す