神前式や地鎮祭など、祝い事の席でいただくのが「御神酒」です。
御神酒は基本的に「日本酒」がよく使われています。
御神酒をいただくと神聖で晴れやかな気持ちになることができます。
では、御神酒とは一体どんなお酒なのでしょうか。
今回は「御神酒」とは何か・なぜ御神酒に「日本酒」が使われるのかについて、どこよりもわかりやすくご紹介します。
「御神酒」とは何か?
御神酒とは、神様にお供えするお酒のことです。
御神酒の読み方は「おみき」、または「ごしんしゅ」ともいいます。
呼び方の使い方は神様にお供えする時には「ごしんしゅ」、その後祭礼の参列者に振る舞われる時には「おみき」と呼ばれます。
ちなみに「神酒(みき)」とはお酒の美称・敬称のことです。
本来の意味は「尊い方、貴い方にお供するお酒」という意味です。
一般的には御神酒には日本酒がお供えされています。
神社によっては御神酒ではなく「國酒(こくしゅ)」といいます。
地域によっては日本酒以外がお供えされている神社があり、九州の一部では焼酎、沖縄では泡盛がお供えされています。
「御神酒」は神饌の1つ
御神酒は神饌の1つです。
神饌の読み方は「しんせん」と読みます。
または御饌(みけ)ともいいます。
神饌とは神前にお供えするお酒や食べ物のことです。
神饌には主にお米・お酒・お餅・海魚・川魚・野鳥・水鳥・海菜・野菜・果物・お菓子・お塩・お水・その他地域の収穫物などがお供えされます。
「御神酒」に日本酒が使われている理由
御神酒に日本酒が使われている理由は、神道において日本酒の主原料であるお米が神聖なものだからです。
日本酒は神聖なお米からつくられていることから、神様へのお供え物としてふさわしいとされています。
「御神酒」がお供えされる祭礼とは?
御神酒がお供えされる祭礼には次のものがあります。
❶お正月
お正月には神社・神宮で御神酒がお供えされます。
その後御神酒は初詣に訪れた参拝者に振舞われます。
お正月に御神酒をいただく理由は御神酒で身を清め、一年間の無病息災を願うためです。
ちなみにお正月に飲むお酒に「お屠蘇(おとそ)」があります。
お屠蘇はお正月にお酒を飲む中国発祥のならわしで「一年間の邪気を払い長寿を願って正月に呑む縁起もの」です。
そのため御神酒とはまったく関係がありません。
❷神前式
神前式には神社・神宮で御神酒がお供えされます。
神前式では「三々九度(さんさんくど)」で新郎新婦が御神酒を酌み交わします。
神前式とは神社・神宮でおこなわれる日本の神様に新郎新婦が夫婦の誓いをたてる結婚式のことです。
神前式の起源は明治33年日比谷大神宮(現東京大神宮)で行われた大正天皇のご成婚の儀が起源といわれています。
三々九度とは三つの盃で、それぞれ三回ずつ御神酒を酌み交わす儀式のことです。
❸初宮参り
初宮参りでは御神酒は神社・神宮にお供えされます。
初宮参りとは子どもの生後1カ月目のお宮参りのことです。
神社で祈祷(きとう)を行った後に、御神酒が振舞われます。
❹七五三
七五三では御神酒は神社・神宮にお供えされます。
七五三とは三歳の女の子、五歳の男の子、七歳の女の子が神様に成長を感謝しお祝いをする行事のことです。
毎年11月15日におこなわれます。
御神酒は神社で祈祷の後に振舞われたり、最近は瓶にいれた御神酒を持ち帰って家で飲む方も増えています。
❺地鎮祭
地鎮祭では御神酒は特設の神棚にお供えされます。
地鎮祭とは家を建てる前に行う儀式のことです。
内容は家を建てる土地に神主を招いて、家を建てる土地の神様にその土地を使用する許しをもらい、工事の安全を祈願するものです。
地鎮祭では、奉献酒(ほうけんしゅ)と呼ばれる御神酒がお供えされます。
一般的にお供えされた御神酒は地鎮祭終了後にお施主さんが持ち帰ることになっています。
❻上棟式
上棟式では御神酒は特設の神棚にお供えされます。
上棟式とは、住宅の棟木(むなぎ)が上ったことを祝う儀式のことです。
簡単にいうと、住宅の骨組みが完成したことを祝う儀式です。
内容は地鎮祭とほぼ同じで、御神酒は乾杯の後、参加者全員に振舞われます。
❼厄除け
厄除けでは御神酒は神社にお供えされます。
厄除けとは、災厄や邪気が寄ってこないように祈願・祈祷する儀式のことです。
一般的に御神酒が振舞われるタイミングは祈願・祈祷が終わった後です。
神様にお供えされる5種類のお酒
神様にはお酒が御神酒としてお供えされます。
こちらでは神様にお供えされる5種類のお酒についてそれぞれご紹介します。
❶白酒
白酒とはどぶろくなどのように白く濁ったお酒のことです。
白酒の読み方は「しろき」と読みます。
白酒は宮中の新嘗祭(にいなめさい)・大嘗祭(だいじょうさい)、神宮の神嘗祭(かんなめさい)など、重要なお祭りの際にお供えされます。
❷黒酒
黒酒とは白酒(しろき)に木灰(きばい)を加えて、黒色にしたお酒のことです。
黒酒の読み方は「くろき」と読みます。
黒酒も白酒と同じように宮中の新嘗祭・大嘗祭、神宮の神嘗祭など、重要なお祭りの際にお供えされます。
❸醴酒
醴酒とは、蒸し米に麹を加え一晩でつくるお酒のことです。
醴酒の読み方は「ひとよざけ・れいしゅ」と読みます。
❹濁酒
濁酒とは、どぶろくのことです。
濁酒の読み方は「にごりざけ・だくしゅ・どぶろく」と読みます。
現在でも濁酒は全国で40社ほどの神社が自前でつくっています。
❺清酒
清酒とは日本国内の材料を使い、日本国内でつくられた日本酒のことです。
清酒の読み方は「きみざけ・せいしゅ・すみざけ」と読みます。
ちなみに伊勢神宮など数社は清酒の酒造免許を持っており、現在も外部委託してつくっています。
まとめ
今回は「御神酒」とは何か・なぜ御神酒に「日本酒」が使われるのかについてご紹介しました。
日本酒は単なるお酒ではありません。
御神酒となることで、神様とのつながりを象徴する神聖なお酒です。
ぜひさまざまな祭礼で、日本酒の御神酒を酌み交わしてみてはいかがでしょうか。



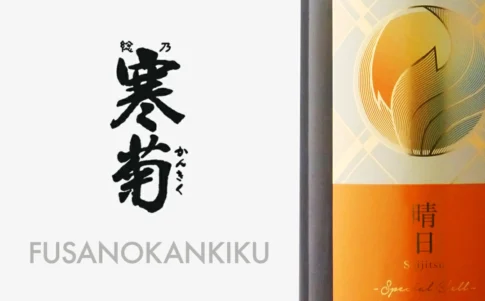








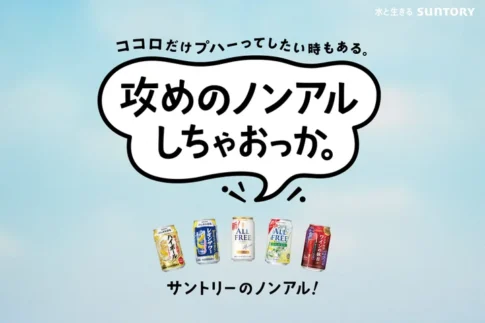
コメントを残す