日本酒の革命児といわれているのが「獺祭」です。
獺祭は山口県の人口わずか300人超えの限界集落でつくられています。
ところが現在はニューヨークやパリなどの大都市で大人気です。
しかも海外では1本10万円以上で売られています。
では、獺祭とは一体どんなお酒なのでしょうか。
今回は旭酒造がつくる日本酒「獺祭」とは・歴史・特徴・名前の由来について、どこよりもわかりやすくご紹介します。
獺祭をつくる「旭酒造」とはどんな酒蔵なのか?
獺祭をつくる「旭酒造(あさひしゅぞう)」は山口県岩国市周東町獺越(おそごえ)にある酒蔵です。
創業は1948年1月です。
獺越は人口300人超えくらいの限界集落で、もともと酒処ではありません。
旭酒造の代表ブランドは日本酒の革命児「獺祭」です。
獺祭の読み方は「だっさい」と読みます。
旭酒造の2022年度の売上は150億円超えでした。
旭酒造の売上の特徴は獺祭をつくればつくるだけすぐに売れてしまうということです。
旭酒造の売上は日本酒の売上低迷とは反比例で売れ続けています。
「旭酒造」の歴史
旭酒造の起源は江戸時代の1770年頃です。
その後、現会長で3代目社長の桜井博志氏の父博治氏が1948年に5つの酒蔵を合併して現在の旭酒造をつくりました。
3代目の桜井博志氏は1976年に旭酒造に入社します。
ところが父と意見が合わなくなり一度退社して石材業を始め、業績は好調でした。
1984年父博治氏が亡くなったことで再度旭酒造に戻り後を継ぐことになります。
ただし当時の旭酒造の業績は最悪で、前年比85%減で、倒産寸前でした。
桜井博志氏は旭酒造の業績を上げようとさまざまな施策をうちますが、ことごとくハズレます。
そんな中、石材業で学んだ「品質が良いものは必ず売れる」という考えを思い出します。
桜井博志氏はそれまで普通酒99%だった酒づくりを辞め、精米50%以下の大吟醸だけをつくることに決めました。
これが「獺祭」が誕生したきっかけです。
「旭酒造」の特徴
獺祭をつくる旭酒造は一般的な酒蔵とはまったく違うタイプの酒蔵です。
こちらでは旭酒造の特徴についてご紹介します。
❶純米大吟醸酒のみに特化
1つ目の特徴は純米大吟醸酒のみに特化していることです。
一般的な酒蔵は普通酒から大吟醸酒までバラエティー豊かな商品のラインナップをしています。
その理由はラインナップが豊富でないと、どのグレードのお酒が売れるかわからないからです。
ちなみに旭酒造は獺祭以前は普通酒づくり99%の酒蔵でした。
ところが旭酒造はそれまでどこもやったことがなかった「純米大吟醸酒」のカテゴリー1本に絞った獺祭の販売を始めました。
❷杜氏が居ない
2つ目の特徴は杜氏(とうじ)が居ないことです。
現在も一般的な酒蔵は杜氏がお酒をつくっています。
杜氏とはお酒づくりの専門家で酒職人のことです。
ところが旭酒造はかつてビール事業に失敗したことが原因で杜氏が離れてしまいました。
そのため2000年から杜氏無しでの酒づくりをおこなっています。
杜氏の代わりにお酒をつくっているのはすべて旭酒造の社員たちです。
ちなみに彼らは「蔵人」と呼ばれています。
❸四季醸造
3つ目の特徴は四季醸造(しきじょうぞう)であることです。
四季醸造とは年間を通して酒づくりをおこなうことです。
年間を通して酒づくりをおこなっているのは大手酒造メーカーだけで、一般的な酒蔵は「寒づくり(かんづくり)」で冬場にしかつくりません。
旭酒造は数階建てのビルの中に酒蔵をつくり、1年365日1日24時間温度管理をしてお酒をつくっています。
「獺祭」とは何か?
獺祭とは現在日本で最も高品質な日本酒のことです。
また値段も日本一です。
現在はさまざまなカテゴリーがありますが、発売当初は「純米大吟醸」のみでした。
一般的な酒蔵は「酔うための酒」「売るための酒」をつくっていますが、旭酒造は「味わうための酒」をつくっています。
この「味わうための酒」として実現したのが獺祭です。
「獺祭」の名前の由来とは?
獺祭の名前の由来は2つあります。
どちらも由来です。
1⃣獺(かわうそ)の祭り説
獺が捕らえた魚を河岸に並べ、それがまるで祭りをするかのように見えることから獺祭と呼ばれたことにヒントを得て獺祭と名付けられました。
2⃣正岡子規の俳号説
明治の文豪正岡子規が自らを「獺祭書屋主人」と号したことからヒントを得て獺祭と名付けられました。
「獺祭」の特徴
こちらでは獺祭の特徴についてご紹介します。
❶精米歩合23%
1つ目の特徴は精米歩合23%のお酒であることです。
精米歩合23%とは玄米を精米して残ったお米の部分が23%ということです。
精米歩合23%の獺祭が誕生するまでは精米歩合24%が最大でした。
獺祭は24%を上回ったことで、当時大きな話題になり、今日の隆盛のきっかけになります。
❷もろみの搾りに遠心分離を採用
2つ目の特徴はもろみの搾りに遠心分離を採用したことです。
獺祭のもろみの搾りには業界初の遠心分離が採用されました。
これにより本来純米大吟醸が持つ香りやふくらみなどを余すところなく表現することに成功します。
❸正規取扱店のみに直接卸し
3つ目の特徴は正規取扱店のみに直接卸しをしていることです。
獺祭は品質を落とさないため、価格を適正価格にするために正規取扱店約630店舗にのみ直接卸す方式をとっています。
まとめ
今回は旭酒造がつくる日本酒「獺祭」とは・歴史・特徴・名前の由来についてご紹介しました。
獺祭はフランス料理の大家ジョエル・ロブションとコラボしたことで、高級ワインと肩を並べる存在になりました。
欧米では1本10万円、レストランで頼むと1本30万円もかかるといわれています。
獺祭はもはや、日本酒を超えた存在になったといえます。
ちなみに日本では正規取扱店で買うと5000円ほどで買うことが可能です。










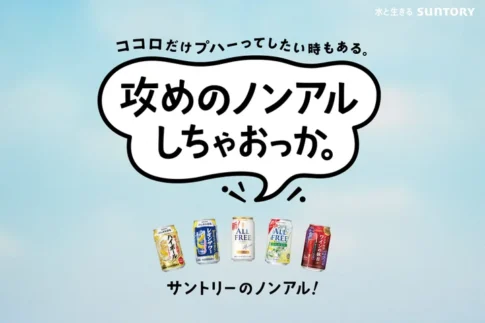
コメントを残す