よりフレッシュな日本酒をお探しの方におすすめするのが「生酒」です。
生酒は一般的な日本酒と若干違う工程を経てつくられます。
そのため一般的な日本酒よりもフレッシュでフルーティーな味わいが特徴です。
では、生酒とは一体どんなお酒なのでしょうか。
今回は、日本酒の「生酒」とは・生酒の起源・工程・特徴・旬の時期について、どこよりもわかりやすくご紹介します。
「生酒」とは何か?
生酒とは一度も火入れをしていないお酒のことです。
生酒の読み方は「なまざけ・なましゅ」と読みます。
また「本生(ほんなま)」「生々(なまなま)」と呼ばれることがあります。
生酒は日本酒の中では「生ビール」に相当するお酒です。
日本酒は大きく分けると火入れをしない「生酒」と火入れをした「火入れ酒」に分けられます。
火入れとは何か?
火入れとはお酒を60〜65℃くらいで、加熱処理をする工程のことです。
日本酒に火入れをする目的は次の2点です。
❶糖化酵素や酵母の失活
1つ目の目的は糖化酵素や酵母の失活です。
日本酒は火入れをしないまま「保存」または「瓶詰め」をしてしまうと、お酒は容器の中で糖化や発酵がすすみます。
糖化がすすむと甘味が強いお酒になります。
また発酵がすすむとアルコール度数が高く辛口度が高いお酒になり、容器の中でチグハグなお酒ができあがってしまうかもしれません。
そうならないために丁度よい味わいの時に火入れをして糖化酵素や酵母を失活させます。
❷火落ち菌の殺菌
2つ目の目的は火落ち菌の殺菌です。
日本酒づくりの大敵といわれているのが「火落ち菌(ひおちきん)」です。
もし日本酒の中で火落ち菌が繁殖すると、お酒の色を白くにごらせ、不快な香味を生じさせます。
そうなると日本酒としては売ることができません。
火入れをすることで火落ち菌を殺菌することができ繁殖を防ぐことが可能です。
「生酒」の起源
生酒の起源は室町時代末期以前までです。
その理由は室町時代末期以降に火入れの技術が誕生したからです。
もともと日本のお酒は「生酒」が基本でした。
お酒は祭礼やお祭りがあるたびごとにつくられていました。
ただし保存技術がないので、もし飲み残すと翌日には酸っぱくなり、味も香りも急激に劣化して飲めなくなります。
そのためすべてのお酒は祭礼や祭りの当日に飲み干すというのが当時のしきたりでした。
その場で飲み干してしまうお酒のことを「待ち酒」といいます。
「生酒」の復活
日本で生酒が再び復活したのは昭和56年(1981年)です。
それ以前の日本は室町時代末期以降に火入れの技術が誕生したこと、江戸中期に寒造りが定着したことなどから、生酒が衰退していき、火入れ酒が主流になりました。
ところが昭和が終わりになると、酒蔵で生酒を飲んだ方が「もう一度搾りたての日本酒を飲みたい」「真夏にキンキンに冷えた生酒を飲みたい」というリクエストが多く酒造メーカーに寄せられます。
この声を受け、月桂冠が本格的に生酒を商品化することに成功し販売を開始しました。
こうして一時衰退していた生酒が日本で再び復活を果たします。
「生酒」ができる工程
こちらでは生酒ができる工程についてご紹介します。
わかりやすいように「もろみづくり」の後からの工程からご説明します。
❶もろみづくり
❷発酵(もろみを発酵させること)
❸上槽(もろみを搾り、原酒と酒粕に分けること)
「上槽」の工程が終わったお酒が「無濾過生原酒」です。
❹無菌濾過(微生物を除去しながらもろみを濾過すること)
❺無菌充填(微生物を除去しながら瓶詰すること)
❻出荷
このように生酒は工程の途中で1回も火入れがないまま出荷されます。
「生酒」の特徴
こちらでは生酒の特徴についてご紹介します。
❶味わい
生酒の味わいの特徴はフレッシュでフルーティーな味わいであることです。
いかにも搾りたてで、瑞々しい味が楽しめます。
よりお米本来の旨味を感じたい方は生酒純米酒がおすすめです。
❷香り
生酒の香りの特徴は新米のような初々しい爽やかな香りがすることです。
また米麹の甘い香りもふわっと鼻を通り抜けていきます。
酵母が活発に活動していることから時間とともに複雑な香りに変化していくことを楽しむことができます。
❸口当たり
生酒の口当たりの特徴は炭酸ガスが豊富なことからスパークリング風のシュワッとした口当たりがすることです。
「生酒」の旬の時期とは?
生酒の旬の時期は2回あります。
1⃣春先
1つ目は春先の新酒の出荷時期です。
この時期は搾りたての生酒を楽しむことができます。
2⃣夏場
2つ目は夏場です。
この時期は新酒を一時低温貯蔵したものが出荷されます。
発酵がすすみ熟成した生酒を飲むことができます。
まとめ
今回は、日本酒の「生酒」とは・生酒の起源・工程・特徴・旬の時期についてご紹介しました。
もともと生酒の試飲は酒蔵めぐりの目玉商品でした。
ところが現在は多くのユーザーが生酒の魅力に気づいたことから、毎年多くの蔵元が生酒を発売するようになりました。
まだ一度も生酒を飲んだことがない方は、ぜひ一度生酒を飲んでみることをおすすめします。












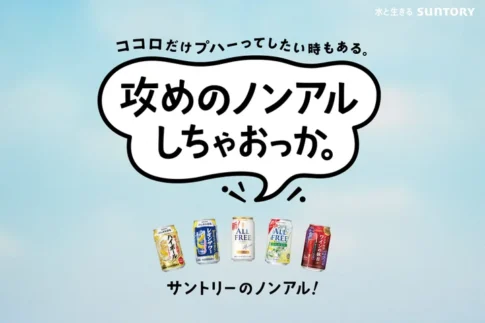
コメントを残す