日本酒をつくっている酒蔵の人が聞くとゾッとする「菌」があります。
それは「火落ち菌」です。
もし酒蔵で火落ち菌が発生すると大変なことになります。
では、火落ち菌とは一体どんなものでしょうか。
今回は日本酒に発生する「火落ち菌」とは・火落ち菌の原因・前対策・後対策について、どこよりもわかりやすくご紹介します。
そもそも「火落ち菌」とは何か?
火落ち菌とは乳酸菌の一種のことです。
火落ち菌の読み方は「ひおちきん」と読みます。
別名「火落ち乳酸菌」といいます。
火落ち菌の特徴はコウジカビが生成するメバロン酸(火落ち酸)を栄養源としている菌という特徴があります。
1⃣コウジカビ
コウジカビとは「麹菌」のことです。
麹菌とは麹(こうじ)をつくるための糸状菌のことになります。
日本酒づくりにはコウジカビは必須の菌です。
2⃣メバロン酸
メバロン酸とはイソプレノイド生合成の重要な中間体のことです。
メバロン酸は別名「火落ち酸」ともいいます。
火落ち菌はメバロン酸を栄養源として増殖をします。
「火落ち」とは何か?
火落ちとは日本酒が貯蔵中に急激に腐敗することです。
また日本酒が腐敗することを「腐造(ふぞう)」といいます。
日本酒が火落ちすると次のような現象が起こります。
1⃣日本酒が白濁する
2⃣日本酒が酸化する
3⃣日本酒からツンとするような特異臭がする
4⃣日本酒の味わいが酢のように酸っぱい味わいになる
「火落ち菌」の種類とは?
火落ち菌には次の3種類があります。
それぞれご紹介します。
1⃣ホモ型真性火落菌
ホモ型真性火落菌とは、火落ち菌の中でも最も強い菌です。
アルコール度25%でも生育が可能です。
2⃣ヘテロ型真性火落菌
ヘテロ型真性火落菌の特徴は増殖の際にガスを発生させる菌です。
ホモ型真性火落菌の次にアルコール耐性が強い菌です。
3⃣火落性乳酸菌
火落性乳酸菌とは中性 の加糖肉汁培地に良く生育する菌です。
アルコール耐性は3つの菌の中で一番低い菌です。
4⃣火落ち菌の種類についてのまとめ
一般的に火落ち菌は6%程度のアルコール度数が最適な生育環境といいます。
そんな中、ホモ型真性火落菌はアルコール度数25%でも余裕で生育してしまう強力な菌です。
ちなみに火落ち菌は発生する菌の種類によって腐敗のタイプが異なります。
違いの特徴は見た目・香り、酸の生成が違います。
「火落ち」したお酒は飲めるのか?
火落ちしたお酒自体は飲めます。
その理由は火落ち菌が入ったお酒を人が飲んでも人体には影響がないからです。
ただしニオイが臭く、味が酸っぱいのでうまくはありません。
「火落ち」はいつ頃から発生していたのか?
日本酒の火落ちが発生し始めたのは、日本酒がつくられるようになってから発生していたといわれます。
もともと日本酒は甕や壺でつくられていました。
その後、木桶や木樽でつくられるようになります。
ところが木桶や木樽は内部の洗浄が難しく、当時は頻繁に火落ちが起きていました。
酒蔵で一度火落ちが起きると、火落ち菌が消滅するまで何年もかかり、酒蔵によっては廃業を余儀なくされます。
それほど昔の酒づくりは火落ち菌との戦いでした。
「火入れ菌」が増殖する3つの原因
火入れ菌が増殖する原因は次の3つです。
それぞれわかりやすくご紹介します。
❶アルコール度数が低いから
1つ目の原因は日本酒のアルコール度数が低いからです。
火落ち菌は25%程度のアルコール度数でも生育が可能な菌がいます。
一般的な生原酒は20%くらいなので簡単に増殖してしまいます。
❷日本酒の品温が高いから
2つ目の原因は日本酒の品温が高いからです。
火落ち菌は高い温度の時に特に繁殖します。
そのため夏場や室温が高くなると、日本酒自体の温度も高くなるので繫殖しやすくなります。
❸容器の衛生状態が悪いから
3つ目の原因は容器の衛生状態が悪いからです。
以前の酒づくりは木桶や木樽が使われていたことから頻繁に火落ちが発生していました。
このように酒づくりの容器の衛生状態が悪く、清潔さとはほど遠い環境であれば火落ちの温床となります。
「火落ち菌」を発生させないための前対策
こちらでは火落ち菌を発生させないための前対策についてご紹介します。
❶火入れ
1つ目の前対策は火入れです。
火入れとは日本酒を加熱殺菌することです。
火入れのやり方は日本酒を約60〜65度の温度で湯煎をして、火落ち菌などの菌を死滅させる方法です。
この時、酵素や酵母の働きを止めて品質の安定化も同時に行います。
❷容器の洗浄・殺菌
2つ目の前対策は容器の洗浄・殺菌です。
火落ち菌は日本酒づくりの環境がとても生育しやすいので簡単に増殖します。
もし容器が汚れていたり、前作業の後が付いていたりするとそこから繫殖を始めます。
そのため作業前には必ず容器の洗浄・殺菌をしなければなりません。
日本酒づくりを始める前に容器を65℃以上の熱湯で洗浄する必要があります。
そうすることで火落ち菌が死滅します。
「火落ち菌」が発生した時の後対策
こちらでは火落ち菌が発生した時の後対策についてご紹介します。
火落ち菌が発生した時の後対策は、すぐに火入れをすることです。
ただし通常の火入れの温度よりも高い70℃以上でおこなう必要があります。
またその他の作業もすぐに止め用具・容器の温水による洗浄・殺菌をおこないます。
まとめ
今回は日本酒に発生する「火落ち菌」とは・火落ち菌の原因・前対策・後対策についてご紹介しました。
最近の酒蔵の仕込みタンクにはホーロータンクとステンレスタンクが使われています。
また洗浄・殺菌技術、衛生管理方法も向上してきました。
そのためほとんど火落ち菌が発生しなくなりました。
ただし酒づくりの環境は火落ち菌が最も快適に過ごせる環境なので、酒蔵は常日頃からの衛生管理を徹底する必要があります。












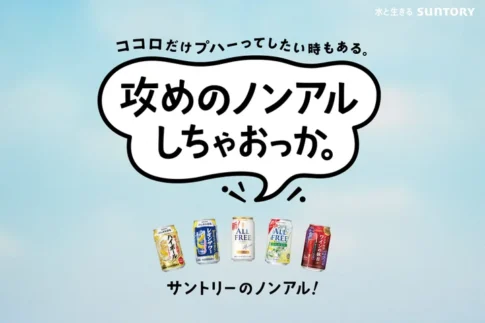
コメントを残す